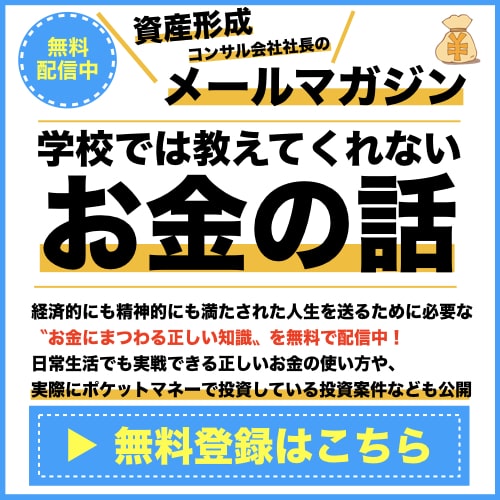医療費控除
今日は「医療費控除」について書いてみます。
医療費控除は会社員の方、個人事業主の方に当てはまる還付の一つなので、対象の方はぜひ最後までお読みください。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間の医療費を一定額以上支払った場合に適用され、納めた税金の一部が戻ってくるというものです。
そして、医療費控除は自分自身の医療費分だけではなく、扶養している家族の分も計上することができます。
一定額以上支払った場合と記載しましたが、使用した医療費が全額還付対象になるわけではありません。
そして、対象になるもの/ならないものもあるので説明していきます。
医療費控除の対象になるもの・ならないものは?
対象になる
・病気の治療のために必要な費用
・薬代
・検査費
・出産
・交通費
対象にならない
・人間ドック、健康診断
・健康促進のためのビタミン剤など
・美容整形
・病院までのガソリン代
・駐車場代
大きく分けると、上記のようになります。
少しだけ補足をすると・・・
交通費は、バスや電車などの公共交通機関での移動費を含めることができますが、タクシー代金は基本的に対象外です。(公共交通機関が利用できない場合は除く)
領収書が発行されないものも多くありますが、通院のためにかかった交通費として合計金額を申請することが可能です。
そのため、領収書が発行されない場合は、日時や公共交通機関名、移動費などをメモしておいたほうがいいですね。
そして、人間ドックや健康診断などの予防的な医療受診は対象外です。
しかし、人間ドックや健康診断をきっかけに病気が見つかった場合は、人間ドック費用も医療費控除の対象となるようです。
病気の予防や健康増進は対象外ということを覚えておいたら分かりやすいかもしれません。
医療費控除を受けることができる人は?
確定申告で医療費控除を受けることができるか、できないかは所得によって異なりますが、
一番簡単な目安は「1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうか」です。
それでは、医療費控除を受けるための条件を紹介します。
◆控除申請をする年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
※年内に治療を受けていたとしても、支払いが翌年になる場合はその年の医療費控除の対象にはなりません
◆医療費控除の額は、実際に支払った医療費等の合計額から以下(1)と(2)の金額を差し引いた額
(1)生命保険などから支給される入院給付金などから支給される療養費などの合計額
(2)10万円(or 5%)
※(2)の補足
・10万円 / 所得金額が200万円以上の場合
10万円を医療費控除として認めることができます。
所得金額が200万円だった場合は、10万円を超える医療費分を還付申告することができます。
・5% / 所得金額が200万円未満の場合
所得金額の5%を医療費控除として認めることができます。
医療費控除額の計算
次に、医療費控除額の計算式は以下になります。
医療費控除額 = [その年に支払った医療費の合計額]-[保険金などで補填される金額] - [10万円 or その年の総所得金額×5%(どちらか少ない額)]
※医療費控除額 = 還付される金額ではないのでご注意ください。
これから還付される金額についても説明していきます。
医療費控除の還付金計算
所得金額によって、還付額は変わってきます。
所得金額が大きい人ほど、還付金額も大きくなります。
| 課税所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
「還付金額」は上記表の所得税率を使い「医療費控除額に所得税税率をかけた額」で算出することができます。
還付金額 = [医療費控除額] × [所得税率(7段階のいずれか)]
▲この金額が実際に還付される(手元に戻る)金額となります。
医療費控除の申告のために必要な書類
1.医療費控除の明細書
2.確定申告書(AもしくはB)
確定申告書にはAとBがの2種類が存在します。
どちらか1つ必要となります。
3.源泉徴収票
こちらは会社員の場合必要となります。
4.医療通知書
セルフメデュケーション税制とは?
医療費控除と比較されるものに「セルフメディケーション税制」と呼ばれるものがあります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についても簡単に紹介しておきます。
これは、平成29年1月からスタートしたものです。
健康診断や予防接種などを受けている人が、ドラッグストアや薬局で対象となる医薬品を年間12,000円以上購入した際に、所得控除を受けることができるというものです。
医療費控除は、自己負担した医療費の合計が10万円を超えなければ控除対象外でしたが、セルフメディケーション税制は対象になる方も多くいるはずです。
医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできないので、確定申告の際はどちらか1つを選択してください。
セルフメディケーション税制については、厚生労働省のHPで以下のように説明されています。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
上記の文章の中で補足します。
「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」とは?
健康診査や予防接種、がん検診などを行っている場合のことをいいます。
実際に「健康の保持増進及び疾病の予防」に取り組んでいることを証明する必要がありますので、確定申告の際には健康診断の結果を提出する必要があります。
「スイッチOTC医薬品」とは?

医師の処方箋がなくてもドラッグストアや薬局で直接購入できる医薬品のことをいいます。
スイッチOTC医薬品は対象医薬品のパッケージに上記のマークが掲載印刷されています。
ただし、このマークは掲載が義務化されているわけではないので、マークが付いていなくても対象となるOTC医薬品もあります。
店頭で確認すると教えてくれるので、スイッチOTC医薬品を選ぶことをお勧めします。
控除額は?
セルフメディケーション税制の控除限度額は88,000円になります。
最後に
確定申告が必要なものには以下の3つがあります。
・医療費控除
・雑損控除
・寄付金控除(※ふるさと納税は寄付金控除の1つ)
雑損控除や寄付金控除についても詳しく記事にまとめてみたいと思います。